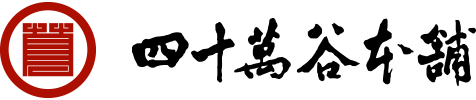いずしについて
魚と野菜を塩、米、糀で漬け込んだものを「いずし」と呼び、発酵を必要とするすしの一つです。かぶら寿しもこの「いずし」の一種であると言えます。「いずし」は東北から北陸の日本海側に分布し、また韓国の日本海側にも「いずし」に近い「シッケ」というものがあり、環日本海文化の一つと言っても過言ではありません。江戸時代の料理書「伝演味玄集」(1745年)には、「生鮓」として、「魚も青物も塩をして桶に入れ」と、魚と野菜を一緒に漬けた記述があり、また「料理珍味集」(1764年)には、「若狭ニシン鮓」として、ニシン、大根などを麹で漬けたとあることから、少なくとも江戸中期には存在していたことが窺えます。
かぶら寿しの起源
かぶら寿しも「いずし」の一種ですが、実はその起源は定かではありません。加賀藩料理人舟木安信の記録に「塩鰤の鮓」として、塩鰤、大根、かぶらを用いるという記述が見られることから、その原型は江戸時代中期に遡ることができるでしょう。今見るかぶら寿しは、泉鏡花「寸情風土記」(1920年)に、「蕪の鮨とて、鰤の甘塩を、蕪に挟み、麹に漬けておしならしたる」とあることから、遅くとも大正時代には、確立していたようです。
加賀藩とかぶら寿し
かぶら寿しの歴史をひも解いた結果、その原型を加賀藩料理人舟木安信の記録「塩鰤の鮓」に見ることができました。私達は舟木伝内包早、安信親子にスポットを当てた映画「武士の献立」が公開された際に、地元新聞社と協力し「かぶら寿し」のルーツとも思われる料理の復元に挑みました。
1. 料理人の記録
参考にしたのは、舟木安信の「塩鰤の鮓」と、これより約140年後のやはり加賀藩お抱え料理人である小島為善の「塩鰤当座鮨」という製法です。
・作身一夜六時水に浸し置き仕込み、廿日ばかりにて用うべし。取り合わせ大こん、蕪切って薄塩致し用うべし。(塩鰤の鮓)
・長さ一寸五分、厚三分、中五分ばかり。朝塩出し暁方宜しく候、飯少し和やかにして洗、しほ交、其外子細なし。(塩鰤当座鮨)
2. 復元の姿録
復元したものは、現在のかぶら寿しと違う点がいくつかあります。
_糀を使わない
現在は、糀を使うことが当たり前ですが、史料を読む限りでは両方の記述に糀は現れません。そのためか、発酵期間は20日と現在より長くなっています。どうしても早く仕上げたい時は酢を使い、4~5日で仕上げたようです。
_かぶらに鰤を挟まない
今回の復元は小島為善の記述通り、鰤を短冊状にして仕込みました。かぶらの上に鰤と彩りの人参がある姿にし、現在のかぶらに鰤を挟む姿はとりませんでした。藩主や武士は鰤を隠して食べる必要がない、と想定したのです。※ちなみに現在も、庶民が高価な鰤を隠れて食べるためにかぶらに挟んで食べたという説があります。
3. 史料の空白
では、現在見るかぶら寿しはいつ生まれたのでしょうか?金沢の文豪 泉鏡花は「寸情風土記」(大正9年)でこう記しています。「蕪の鮨とて、鰤の甘塩を、蕪に挟み、麹につけて圧しならしたる。」(寸情風土記)
この「蕪の鮨」が「塩鰤の鮓」が変化したものなのか、それとも併存してこのような作り方があったのか食文化に関わる大きな疑問です。ところが、この疑問を解くための資料は今の所なく、真実は当時の人々のみが知るところとなっています。今回の復元によって少し見えてきたかぶら寿しのルーツ。私たちの復元を、加賀藩の料理人たちはどのように見ていることでしょうか。